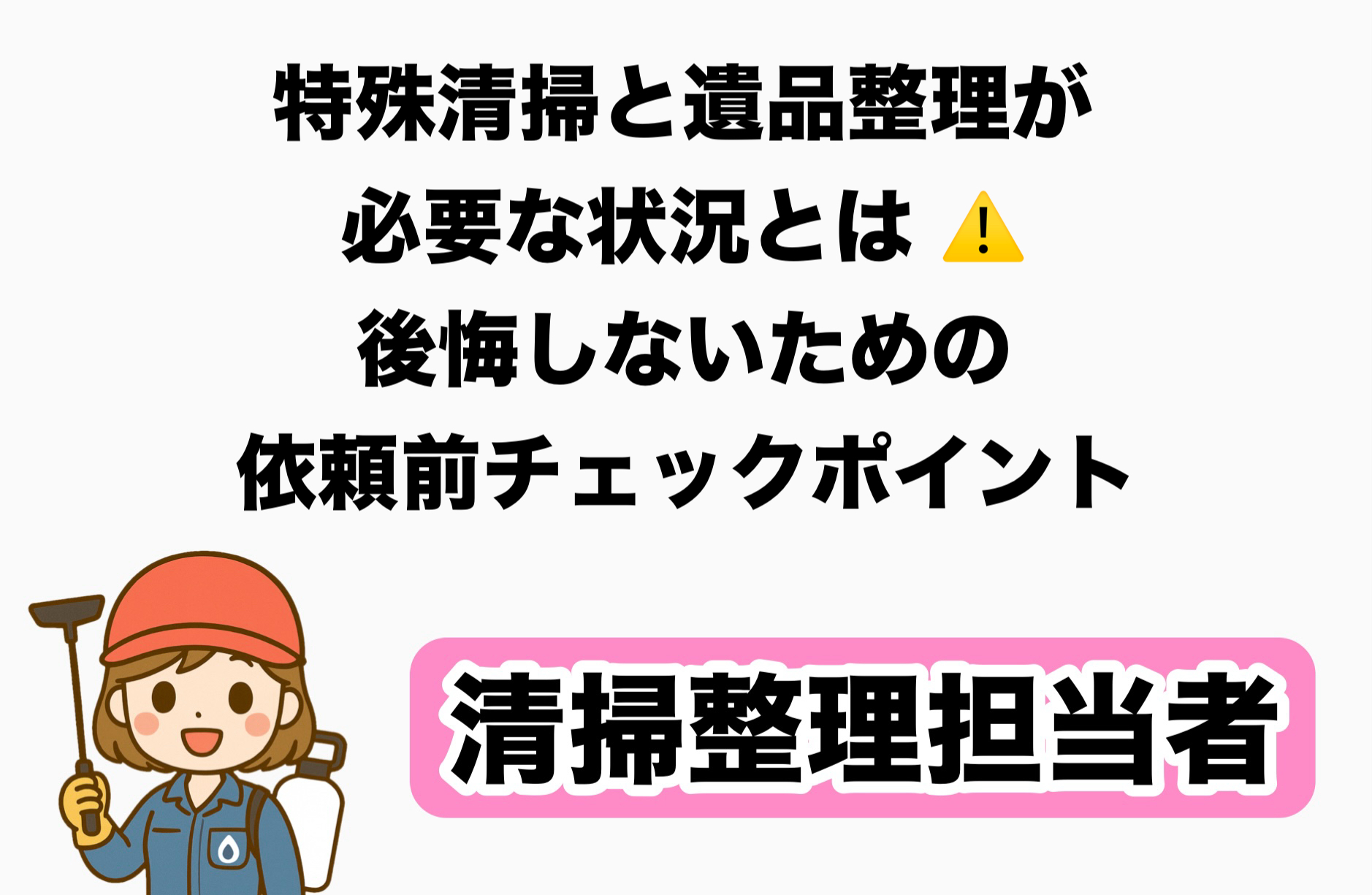最近、「特殊清掃と遺品整理」というワードをネットやニュースでよく目にするようになったと感じませんか?
X(旧Twitter)やYouTube、Yahoo!知恵袋などでも、関連する投稿や相談が目に見えて増えています。
中には「父が孤独死したが、部屋に入れなかった」「遺品整理中に体液が見つかり、自力では対処できなかった」など、現実とは思えないような声も多く寄せられていますね。
このような投稿や報道を見ると「大げさなんじゃないか」と思う方もいるかもしれませんが、実際は年々増えているのが現状です。
国土交通省や厚労省の調査によれば、単身世帯の高齢者やセルフネグレクトが原因で、自宅で亡くなったあとに発見が遅れるケースが増え続けているとされています。
そこで注目されているのが、清掃のプロフェッショナルによる「特殊清掃」と、遺族に代わって持ち物を整理・処分する「遺品整理」という2つの専門サービスです。
この2つの作業は、見た目には似ているようでまったく性質が異なるもので、どちらも「ただの片付け」では済まされない背景があります。

ここでは、なぜ今こうした専門業者のニーズが高まっているのか、その理由と背景を4つのポイントに分けて、初心者の方にもわかりやすくお伝えしていきます✨
増加する「孤独死」「事故物件」でニーズが急拡大中
まず最初にお伝えしたいのが、特殊清掃と遺品整理の需要は確実に右肩上がりだという現実です。
背景にあるのは、高齢化・単身化・地域の孤立です。
実際、東京都監察医務院のデータでは、孤独死として扱われる案件は年間5,000件以上にものぼるとされ、地方都市でも急増している傾向があります。
また、孤独死だけではなく「自死」「事件性のある現場」「突然死による腐敗の進行」などでも、普通の掃除業者では対応できないケースが多発しています。
たとえば、亡くなってから数日以上が経過した場合、床下への体液浸透、虫の発生、異臭などが問題になるため、専門的な装備と技術がなければ作業自体が危険です。
これまであまり可視化されていなかったこうした“重たい現場”が、SNSやメディアによって少しずつ表に出るようになり、「自分の家族も、他人ごとじゃない」と気づく方が増えてきました。

結果として、プロによる対応が“当たり前”の選択肢になりつつあるというわけです。
一般的なハウスクリーニングでは対応できない理由
「じゃあ、ハウスクリーニングの業者に頼めばいいのでは?」と思われるかもしれません。
ですが、特殊清掃は見た目のキレイさを整える作業とは全く異なります。
まず第一に、感染症や害虫のリスクが伴う現場であること。
腐敗が進んでいると、ノロウイルス・肝炎・細菌類などが付着している場合もあり、掃除機やモップだけでは絶対に除去できません。
現場には防護服・マスク・専用薬剤・オゾン脱臭機などが必須になります。
また、異臭は市販の消臭剤では完全に消えません。
壁紙の裏や床材の下にまで臭いが染み込んでいることが多いため、床の剥離・クロスの張り替え・構造材の清掃まで求められるケースもあります。
つまり、通常の清掃会社ができる範囲とはスケールがまるで違うのです。

「汚れを落とす」のではなく、「安全と衛生を回復させる」作業であるという視点が必要ですね。
清掃と遺品整理は「セット」で考える時代へ
以前までは、「まず遺品整理をして、それから掃除」という手順が一般的でした。
ですが、今は両方を同時に依頼する家庭が増えています。
理由としては、臭いや汚染の影響で、遺品の仕分けすらできない状態になっていることが多いためです。
衣類や本、写真アルバムなども、体液や虫の付着があると、素手ではとても扱えません。
「遺品の中に貴重品があるかも」と思っても、自分で探し出せる状況ではないこともあります。
さらに、感情面でのダメージも大きく、「自分では触れられない」「部屋に入るだけで動悸がする」というご遺族も少なくありません。
そういった場面では、清掃と遺品整理を一括で引き受けてくれる専門業者に頼むことが、物理的にも精神的にも助けになります。

中には、「手紙や写真など、大事なものを丁寧に取り分けてくれたおかげで、気持ちに一区切りついた」と話す方もいますよ✨
感情・衛生・法律の3つの視点で考える必要性
最後にお伝えしたいのは、この分野はとても繊細な要素が重なりあっているということです。
まず感情面では、「亡くなった方の生活の痕跡に触れる」作業は、想像以上に心の負担がかかります。
それをいきなり家族が担うのは、とても難しい場合があります。
次に衛生面では、すでにお話ししたようにウイルスや臭気の問題があるので、専門的な消毒・防臭対策がなければリスクを残したままになります。
さらに見落とされがちなのが、法律や手続きの面です。
遺品には貴重品・借用書・金融資産・行政関係の書類などが含まれることがあり、勝手に処分するとトラブルの元になります。
また、作業自体に「産業廃棄物収集運搬許可」が必要なケースもあります。

つまり、この分野は“ただの片付け”とは違う、専門的な対応が求められるジャンルなのです。
清掃と遺品整理が必要になる代表的なケースとは
特殊清掃や遺品整理って、「あ、これも該当するのか…」と感じるようなケースが、私たちの日常の中にもけっこうあります。

ここでは、私たち特殊清掃業者が実際に依頼を受けた中でも多かった代表的な4つのケースを、順番にお話しします。
孤独死・自殺・事件現場などの特殊状況
まず最初に挙げたいのが、孤独死や自死などによって、ご遺体の発見が遅れたケースです。
これは特殊清掃という分野が一気に広がったきっかけでもあります。
理由としては、体液・血液・腐敗臭が部屋中に広がるため、通常の掃除では対応ができないからです。
ご遺族が現場に立ち入る前に、感染症のリスクを抑えるための除菌・脱臭・害虫処理などを最優先で行う必要があるのが現実です。
実際にあった例では、夏場に数日間発見が遅れたために床が変色し、マンションの下の階まで体液が漏れていた…なんてことも。
そうなると、ご遺族の手には負えないのはもちろん、管理会社や近隣住民とのトラブルにもつながります。

だからこそ、専門の業者に依頼して、しっかりとした技術と装備で処理することが重要になります。
ゴミ屋敷・セルフネグレクトによる生活環境崩壊
次に多いのが、「ゴミ屋敷状態になってしまった部屋の清掃と遺品整理」です。
一見するとただの“散らかし”に見えるかもしれませんが、セルフネグレクト(自己放任)によって生活全般を維持できなくなり、食べかけの弁当や腐ったゴミが何ヶ月も放置されているようなケースもあります。
そうなると、室内は害虫・悪臭・カビの温床になっていることが多く、場合によっては床や壁が腐食していることすらあります。
また、ご本人が亡くなったあとにそのまま残された場合、遺族が室内に入るのも難しい状況になってしまいます。
私たちが実際に対応した現場では、「実家に帰ったら部屋がゴミで埋まっていた」「母の部屋がカビだらけだった」など、想像以上に深刻なケースがほとんどでした。

このような現場では、“清掃”というよりも“環境の再構築”に近い作業が求められるんです。
賃貸退去・売却前に必要な原状回復作業
特殊清掃や遺品整理は「重たい事情がある人の話」と思われがちですが、実は不動産売却や賃貸退去の場面でもよく依頼されます。
たとえば、長年一人暮らししていた親御さんが亡くなり、実家を売ることになった…という場合。
室内には大量の家具、古い衣類、生活ゴミ、仏壇や写真などがそのまま残っていて、どこから手をつけたらいいかわからないという相談が多いです。
さらに、賃貸住宅だと「原状回復」が義務になります。
特に事故物件として扱われるような場合は、臭いや汚れを残したままでは貸し出せないため、専門的な清掃が必要になるのです。

不動産会社や管理会社から直接私たちに連絡がくることもありますが、「費用を抑えたいから直接頼みたい」と個人の方から依頼されるケースも増えていますよ。
相続や家屋解体に伴う遺品分別と処分整理
最後に、相続や解体を前提とした遺品整理です。
「実家を相続したが住む予定がない」「老朽化しているので解体することになった」などの理由で、中の荷物をすべて出さなければならない…でも、家財の量が多すぎてどうにもならないというご相談をよく頂きます。
このケースで特に気をつけなければいけないのが、「どれがゴミで、どれが大切なものか」の判断がとても難しいという点です。
遺言書・通帳・土地関連の権利書・骨董品など、見落とせない書類や財産が混ざっていることも珍しくありません。
だからこそ、「ただ捨てる」作業ではなく、「仕分ける」「確認する」「記録に残す」作業が必要なんですね。
私たち業者は、作業の前にヒアリングを行い、大切なものを丁寧に取り分けてご家族にお渡しする流れを徹底しています。

ご遺族からは「こんなところにへそくりが入っていたとは…」と驚かれることもしばしばです(笑)
特殊清掃と一般的な清掃の違いとは?具体的な作業内容
特殊清掃って、言葉だけ聞くと、プロが丁寧に掃除してくれる…くらいの印象で止まってしまいがちなんですよね。
でも、実際の現場を知る者から言わせてもらうと、特殊清掃は“掃除”というより“環境の回復作業”なんです。
ここでは、特殊清掃の特徴を4つの具体的な観点から掘り下げていきます。

比較対象としてハウスクリーニングの常識を想像して読んでいただくと、違いがより鮮明になるはずです✨
消臭・除菌・体液除去など専門的工程が必要
まず大前提として、特殊清掃の現場には「におい」と「汚染」がほぼ確実に存在します。
これは日常的な掃除ではほとんど扱わない領域で、作業には専用の機材・洗浄剤・手順が必要です。
たとえば、孤独死後の部屋に入ると、強烈な腐敗臭がこびりついており、窓を開けても取れません。市販のスプレーや重曹ではどうにもならないです。
そこで私たちは、オゾン脱臭機・酵素系洗浄剤・バイオ除菌剤などを組み合わせて、においの根本原因から分解する処理を行います。
また、床や布団などに体液がしみ込んでいる場合、それを表面だけ拭き取っても意味がなく、床材をはがして内部の構造材まで洗浄・消毒・乾燥させる必要があることも多いです。

これが一般の掃除との最大の違いかもしれませんね。“見えないところまで徹底してやる”のが特殊清掃の基本姿勢です。
感染症・害虫のリスクとその対策とは
特殊清掃で見落とされがちなのが、「衛生面のリスク」です。
実際、腐敗が進んだ現場には、ノロウイルスや肝炎ウイルス、細菌類が潜んでいる可能性があります。
また、遺体から発生した体液が養分となり、ハエ・ウジ・ゴキブリなどの害虫が大量発生している現場も珍しくありません。
このような環境での作業には、防護服・N95マスク・二重手袋など感染防止の装備が必須です。
そして、単に害虫を駆除するだけでなく、繁殖源(床下や壁の裏)を徹底的に除去して再発を防ぐ処置まで行います。
現場によっては、害虫駆除業者との連携が必要になることもあり、消毒処理後に再点検を複数回行うこともあります。
ここまでやって、ようやく「安全な状態に戻せた」と言えるんですね。

一方、ハウスクリーニングでは、こうした感染症リスクや生物汚染の工程は含まれていません。
作業現場のビフォーアフターとその費用感
読者の方が気になるポイントとして、「費用はいくらかかるの?」という声も多いです。
正直に言うと、現場ごとに大きく変動します。
たとえば、
-
1Kのワンルームでの孤独死(腐敗初期):10万円前後
-
ゴミ屋敷+体液汚染+床材除去が必要なケース:30〜50万円
-
マンション下階への浸透・全面消臭+内装補修:80万円以上
というように、作業内容・日数・機材量で大きく変わります。
一方で、遺品整理だけの作業であれば、作業員2名・1日で5万円〜10万円ということもあります。
重要なのは、見積もり段階で「どこまで対応してくれるか」を明確にしてもらうこと。
中には「遺品回収だけで終了」だったり、「消臭だけ簡単にやっておしまい」だったりする業者もいます。

価格の安さだけで選んでしまうと、あとで“中途半端な状態”が残ることもあるので注意が必要です。
「特殊清掃士」など資格と技術を持つ人材が必要
最後に、人材の観点です。
特殊清掃は、ただモノを動かして掃除機をかけるだけの仕事ではありません。
むしろ、現場での判断力・メンタル・マナー・技術のすべてが求められる仕事です。
そのため、業界では「事件現場特殊清掃士」「遺品整理士」などの認定資格が存在しており、それを取得した作業員が対応するケースが増えています。
もちろん資格があればOKというわけではありませんが、知識と経験の裏付けがあるかどうかを見極めるためのひとつの指標になります。
また、故人への配慮やご遺族への接し方など、人間性が問われる場面も多いので、業者選びの際には「口コミ」「現場対応」「ヒアリングの丁寧さ」なども要チェックです。
実際に、「遺体の話ばかりしてきて不快だった」「淡々とゴミ扱いされた」などの苦情もあります。

専門性だけでなく、“人として信頼できるか”を見て選ぶことが何より大切ですね。
SNSや掲示板でのリアルな声|依頼者たちの本音と後悔
特殊清掃や遺品整理って、実際に体験しないとその大変さってなかなか伝わらないですよね。
だからこそX(旧Twitter)やYahoo!知恵袋、5ちゃんねるやマンション系掲示板などで投稿された“リアルな声”がものすごく参考になります。
ここでは、ネット上に実際にあった投稿内容や、業者側がよく聞く相談内容を元に、依頼者の本音や後悔の声を具体的に紹介していきます。

単なる口コミではなく、感情・失敗・安心感の3点を軸に読み解いてみて下さい✨
「想像以上だった」壮絶な現場に驚いた声(Xより)
「父が孤独死していた部屋に入ったら、ドアを開けた瞬間に吐きそうになった」
「見た目は普通なのに、床下から異臭がしてきて…まさか体液が浸透してたとは」
こうした投稿は、Xを検索すると本当にたくさん出てきます。
中には、写真付きで「現場のヤバさ」を記録している方もいて、においや汚れのレベルが想像の何倍も上をいっていることがわかります。
実際、私たち業者も「一度入ったけど、すぐ出てきてしまったのでお願いします…」と相談されることが多く、ご遺族が直接対応するのは心身ともに厳しい作業だと感じます。

こうした声からも、事前のイメージと現実のギャップがいかに大きいかが伝わってきますね。
「安さで選んだら地獄だった」格安業者の失敗談
次に多いのが、「安さに飛びついた結果、後悔した…」という失敗談です。
「見積もりでは5万円と言っていたのに、作業後に20万円請求された」
「消臭はしたと言っていたのに、数日後にまた異臭が復活」
「遺品を勝手に捨てられてしまった…あとから母の通帳が必要だったのに」
こういったトラブルは“格安”や“即日対応”を謳っている業者に多い印象があります。
作業工程の説明が曖昧だったり、契約書が無かったりするケースもあり、後から「こんなはずじゃなかった」と感じる方が本当に多いです。
中には「実家の大事な仏壇が無断で解体されていた」と怒りの声を上げる方もいました。

やはり、費用の安さよりも“信頼できる説明と対応”が最重要だと実感します。
「救われた気がした」感情面でのサポートが心の支えに
特殊清掃や遺品整理って、実は「技術」よりも「寄り添い」のほうが記憶に残るんです。
「遺体があった場所をお花で飾ってくれたのが泣けた」
「“無理しなくていいですよ”って一言に救われた」
「手紙や写真を丁寧に保管してくれたおかげで、気持ちの整理がついた気がした」
こうした投稿は、XやYouTubeの体験談動画などでもよく語られています。
作業員がただ機械的に片づけるのではなく、ご遺族のペースや気持ちに寄り添ってくれたことが何より嬉しかったという感想が圧倒的に多いです。
正直、私たち業者側からしても「技術的に難しい現場」より、「気持ちをどう受け止めるか」に悩むことが多いです。

でも、“心まで汚れたままにしない”ように寄り添うことこそ、この仕事の本質だと感じています。
清掃業者の“人柄”が依頼満足度を左右するケースも
「来てくれた作業員が感じのいい人で安心した」
「作業中も丁寧に説明してくれて、不安が薄れていった」
「逆に、態度が横柄でムカついたから途中でキャンセルした」
清掃技術や価格も大切ですが、最後に印象を左右するのは“人”です。
ネット上にも、「親身な対応だったから安心できた」「あいさつもなしで作業されたから残念だった」など、業者の“態度”に関する口コミがかなり目立ちます。
特に、遺品整理は感情が揺れやすい場面なので、作業の丁寧さだけでなく、言葉遣いや気配りができるスタッフかどうかが満足度を大きく左右するんですね。

これは私たち業者側も痛感していて、新人教育では「掃除の仕方」だけでなく、「ご家族との向き合い方」まで徹底して教えるようにしています。
依頼前に知っておくべき3つの注意点とは?
「特殊清掃や遺品整理って、どうやって依頼したらいいの?」という声はかなり多いです。
実はここ、トラブルが起きやすい“落とし穴ポイント”でもあるんですね。
作業の内容が専門的であるぶん、契約やお金のやり取りに慣れていないと、業者任せにして後から後悔するケースも少なくありません。
ここでは、依頼前に絶対チェックしておきたい3つの視点をまとめておきます。

「頼んでよかった」と思える依頼をして欲しいので、ぜひ一通り目を通して下さい✨
契約書・見積もり時に確認すべき“法的視点”
まず第一に、「契約書と見積書は、きちんと事前にもらう」これが基本です。
「電話だけで口約束」「メールのやり取りだけ」というのは、あとあとトラブルの火種になります。
実際、過去のトラブル事例として、
-
作業後に「ここも追加で清掃しました」と言って10万円上乗せ
-
作業日当日になって急にキャンセル料を請求された
-
「消臭はオプション」と言われて結局高額請求に
といった事例が国民生活センターなどにも報告されています。
こうした事態を防ぐためにも、作業内容・範囲・料金・日程・キャンセルポリシーなどを明記した書面を取り交わすことが絶対に必要です。
さらに、作業に「産業廃棄物収集運搬許可」が必要かどうかも要確認です。
廃棄物を無許可で処分してしまうと、依頼主側も責任を問われるリスクがあります。

業者がこの許可を持っているかどうかも、必ず確認して下さい。
料金体系の相場と「高額請求トラブル」を避ける方法
2つ目は「金額」についてです。
特殊清掃や遺品整理には明確な“定価”がないため、料金が業者ごとにかなりバラつきがあります。
そのため、相場を知らずに頼むと、思わぬ高額請求に繋がるリスクがあるんですね。
たとえば、
-
1Kの部屋で、遺品整理+消臭作業なら10〜20万円前後
-
ゴミ屋敷清掃+内装剥がしで30〜50万円程度
-
完全リフォーム込みであれば、100万円以上のことも
といった価格感が目安になります。
これより大きく上回っていたり、逆に極端に安い業者には注意が必要です。
また、見積もりの段階では必ず、
-
基本作業費と追加オプションの区別
-
処分費や出張費の含まれ方
-
「消臭」「床下除去」などの範囲の明示
これらが書かれているかを確認しましょう。
ちなみに私たちの現場では、「一社だけで決めないで下さい」と伝えています。

最低でも2〜3社の見積もりを比較して、自分で納得してから決めるのが安心です。
遺品の返却・貴重品の扱いが明記されているかどうか
最後のポイントは「遺品の扱い方」です。
これ、意外と見落とされがちなんですが、“どこまで探してくれるか”が業者によって全然違うんです。
たとえば、
-
通帳・印鑑・遺言書・現金などの「貴重品」を必ず確認・返却してくれるか?
-
写真・手紙・仏壇・アルバムなど、気持ちの整理に関わる品を分別してくれるか?
-
不用品の中にも、リユース可能な物があれば相談に乗ってくれるか?
これらが契約内容や事前説明の中で一切触れられていない場合、作業員の判断で廃棄されてしまう可能性もあります。
実際に「おじいちゃんの手紙が捨てられていた…」「へそくりの場所を知らずに全部回収された…」という投稿も見かけました。
だからこそ、「どんなものは残して欲しいか」「事前に探して欲しい物は何か」を明文化して伝えることがすごく大切です。
また、業者がそのリクエストにどう対応するかも、業者選びのひとつの基準になりますよ。

ここまでの内容を押さえておくだけでも、かなり安心して依頼ができるはずです✨
「立ち直れない」自分に向けた視点|感情整理としての清掃
特殊清掃や遺品整理って、ただ「片付ける」だけじゃないんです。
そこには、心の奥に積もってしまった感情と向き合う時間が、しっかりと流れているように感じます。
実際、ご依頼いただいた方から「何もやる気が起きなかったけど、部屋を片付けていくうちに少しずつ気持ちが落ち着いてきた」と言われることが多いです。

清掃作業は、「感情の整理」のきっかけにもなる――ここでは、そんな側面についてお伝えしていきますね。
清掃を通じて遺族の気持ちが“少しずつ変化”していく過程
最初は「業者に全部任せて、できれば見たくない」という状態だった方が、作業の様子を見ているうちに「やっぱり自分でも触れたいと思った」と言って下さる場面があります。
現場をきれいにしていく工程の中で、「あ、この人はこういうふうに生活してたんだな…」と感じられる瞬間があるんですよね。
たとえば、机の上に残されたメモ、冷蔵庫の中のお気に入りだったであろう調味料、押し入れの奥から出てきた古いアルバム。
それらを目にすることで、悲しみだけではない、その人の“生きた痕跡”を肌で感じられるようになるんです。
そしてそれが、少しずつ「この別れを受け入れよう」という気持ちに変わっていく過程になることもあります。
清掃って、ただの掃除じゃない。

ご遺族が「一歩進むための時間」に変わる力を持っていると思っています。
罪悪感・後悔の感情が和らいだという声
「自分がもっと連絡していれば、こんなことにならなかったかも」
「介護がしんどくて避けていた自分を、今でも責めてしまう」
こうした声、本当に多く聞きます。
遺された側って、どうしても“やれなかったこと”にばかり目が向いてしまうんですよね。
でも、特殊清掃や遺品整理を通して、そういった感情がほんの少し軽くなることがあります。
実際にあった声を紹介すると、
「ずっと後悔してたけど、丁寧に作業してくれた業者の人の姿を見て、“今できることをやってるんだ”と思えて救われた」
「片付け終わった部屋を見たときに、ようやく“ちゃんと送れた気がした”」
こういった言葉を頂くと、私たちも胸が熱くなります。

清掃や整理が、“過去を否定するもの”ではなく、“今を整える手段”になっているんだなと感じます。
「整理=忘れる」ではない、自分なりの向き合い方
よく「整理したら忘れてしまいそうで怖い」というご相談を頂きます。
でも私は、それはまったく逆だと思っています。
むしろ、整理するからこそ「思い出を大切に保管できる」。
部屋の中に散らばったままでは、触れることすらできず、かえって記憶の中で曖昧になっていくんじゃないでしょうか。
たとえば、1枚の手紙を残す。お気に入りだったマグカップを取っておく。
そういう小さな選択が、「忘れないための行動」になります。
整理は、“過去をなかったことにする”作業ではなく、“これからも心の中に置いておくための準備”なんです。
だから、無理に全部捨てなくてもいいし、すぐに決める必要もない。

“自分なりの向き合い方”を探していくことが何より大切なんだと思います。
私の経験:叔父の孤独死に立ち会って感じたこと
少しだけ、私自身の話をさせて下さい。
数年前、叔父が孤独死で亡くなりました。発見が遅れ、部屋の中はもう手がつけられない状態でした。
最初は正直、現場に入るのも怖くて、全部業者に任せようと思っていました。
でも、作業が始まって、机の中から小さな手帳が出てきたとき――それを見て、「あ、この人、こんな風に日々を過ごしてたんだな」と思ったんです。
それからは、自然と一緒に遺品の仕分けを手伝っていました。
怖かったはずの部屋も、最終的には「ありがとう」と言いたくなる場所に変わっていました。
その時強く感じたのは、清掃って、誰かの過去を片付けるんじゃなくて、遺された自分たちの“今”を整える作業なんだということです。

あの経験があったからこそ、今こうしてこの仕事を続けていられるのかもしれません。
専門業者の選び方|信頼できるプロに頼むためのチェックリスト
「どこの業者に頼んでも同じでしょ?」と思っていた方が、作業後に「こんな業者に任せなければよかった…」と後悔するケース、じつは珍しくありません。
特殊清掃や遺品整理は、価格よりも“人”と“信頼”がすべてと言っても過言ではないです。
ここでは、「失敗しないための業者選びのチェックポイント」を、プロ目線でしっかりまとめていきます。

ネット検索だけで決める前に、ぜひ参考にして下さい✨
HP・実績・口コミの見方と評価ポイント
まず最初に確認して欲しいのは、業者の公式ホームページと口コミ情報です。
最近はSNSでも検索される方が増えていますが、X(旧Twitter)やGoogleマップ、みん評、エキテンなども参考になります。
ポイントは、
-
実際の作業写真を載せているか
-
作業事例が具体的か(料金・日数・内容)
-
スタッフ紹介や会社概要に“顔”が見えるか
これらが揃っていれば、実在していること、そして誠実にやっていることの証拠になります。
逆に「料金が激安!即日対応!」とだけ書いてある業者は、詳細をぼかしている可能性が高いので要注意です。
また、口コミは良い意見だけでなく、「悪い評価にどう返信しているか」も見るのがコツです。

誠実に対応しているかどうかで、その会社の姿勢がよく見えてきますよ。
地域対応・24時間体制など柔軟性の比較
意外と見落とされがちですが、「どの地域に対応しているか」「対応時間はどうなっているか」もとても大切なポイントです。
特殊清掃は「明日すぐお願いしたい」「夜間しか立ち会えない」など、時間に融通がきくかどうかで助かるシーンが多いんですよね。
また、対応エリアが全国か地方限定かも業者によって異なります。
たとえば、
-
24時間365日対応か
-
土日・夜間も見積もりや作業が可能か
-
交通費や出張費がどうなっているか
これらを事前にチェックしておくだけで、いざという時に焦らずに済みます。

柔軟に動いてくれる業者は、現場での対応も親切な傾向があるので、選ぶ基準としてはかなり重要です。
資格保有者・損害保険加入の有無も要確認
次に確認したいのが、「資格」と「保険」です。
特殊清掃や遺品整理は専門性が高い作業のため、作業者の知識と対応力に差が出やすいジャンルです。
信頼できる業者は、以下のような資格を保有していることが多いです。
-
事件現場特殊清掃士(一般社団法人事件現場特殊清掃センター)
-
遺品整理士(一般社団法人遺品整理士認定協会)
-
古物商許可(貴重品取り扱いに必要)
また、現場で万が一事故があった場合や物損が発生した際に備えて、損害保険(賠償責任保険)に加入しているかどうかも大事なチェックポイントになります。

「資格はあるけど保険がない」「保険はあるけど現場未経験ばかり」という業者もあるので、両方そろっているか確認しましょう。
「訪問見積もり無料」がある業者が安心
最後のポイントは、「見積もりは訪問してから出してもらうこと」です。
電話や写真だけで料金を提示する業者もありますが、実際の現場状況を見ないと正確な見積もりは出せません。
臭いの強さ・害虫の有無・床や壁の汚染範囲などは、現場ごとに本当に違います。
そこで重要なのが、「訪問見積もり無料」と明記しているかどうかです。
これがないと、「訪問後に料金が発生していた」「作業を断ったらキャンセル料が請求された」というトラブルの元になります。
また、訪問見積もりの際に“担当者の雰囲気”を確認できるのも安心材料になります。

現場での対応力は、こういう初対面の対応にすでに出ていることもありますからね。
よくある質問
ここでは、X(旧Twitter)やGoogle検索、Yahoo!知恵袋などで多く見かける「特殊清掃・遺品整理」に関するリアルな声をもとに、依頼前によくある疑問を一問一答形式でまとめてみました。

初めての方でも安心して読み進められるよう、具体例を交えながらお答えしていきます✨
Q. 特殊清掃の料金はなぜこんなに高いの?
A. 特殊清掃は「臭い」「体液」「感染症リスク」などに対応するため、市販の掃除道具では太刀打ちできない専用機材・薬剤が必要になるんです。
さらに、防護服やオゾン脱臭機なども使うため、人件費や設備コストが反映された価格になります。
安い業者は対応範囲が狭かったり、後から追加請求がある場合もあるので、総額で比較するのがポイントです。
Q. 遺品整理とゴミ処分の違いって何?
A. ゴミ処分は単に“不要物を捨てる”行為ですが、遺品整理は「何を残し、何を手放すか」をご遺族の想いに寄り添って選別・回収・返却まで行う作業です。
業者によっては、「貴重品の探索」「お焚き上げ」「合同供養」などにも対応しており、心のケアの一環として依頼される方も多いですよ。
Q. 孤独死の現場、素人でも掃除できますか?
A. 基本的にはおすすめしません。
腐敗臭・体液・害虫などの問題に加え、ウイルスや菌の繁殖リスクがあります。
防護装備がなければ健康被害を受ける可能性もあるので、特殊清掃のプロに任せるのが安心で確実です。
Q. 遺品整理のとき、立ち会わないとダメ?
A. 業者によりますが、立ち会い不要で完結する業者も増えています。
事前に鍵を預けたり、オンラインで打ち合わせをして遠隔で進める方もいます。
「立ち会うのがつらい」「遠方で行けない」など、事情に応じて柔軟に対応してもらえるかどうかを相談してみるといいですよ。
Q. 家の中から大量の現金や通帳が出てきたらどうなる?
A. 良心的な業者であれば、貴重品として丁寧に保管・返却してくれます。
ただし、事前に「貴重品は返却対象に含まれるのか」を確認し、契約書や作業指示書に書き込んでおくことをおすすめします。
また、古物商許可を持っている業者であれば買取査定の対応も可能です。
Q. 特殊清掃業者にお願いしても消臭できないことはある?
A. 臭いのレベルや浸透状況によっては、一度の作業では完全に取れない場合もあります。
特に床下や壁内部にまで体液が浸透していると、再度の処置や内装補修が必要になるケースも。
見積もり時に「どのレベルまで対応してくれるのか」を確認しておくのが大切です。
Q. 特殊清掃と原状回復の違いは?
A. 特殊清掃は「臭いや汚れを除去して安全な状態に戻す作業」、原状回復は「住宅契約上の義務として、入居時の状態に近づける作業」です。
つまり、特殊清掃は“汚染処理”、原状回復は“修繕・内装工事”という目的の違いがあります。
必要に応じて、両方を別業者で依頼する場合もあります。
Q. 特殊清掃のあと、すぐに住めるようになりますか?
A. 臭い・害虫・感染リスクが取り除かれていれば、数日後には住めるようになるケースが多いです。
ただし、フローリング張り替え・壁紙補修・設備工事が必要な場合は、1〜2週間かかることも。
状況に応じて、作業完了時に「居住可能レベル」かどうかを報告してもらうと安心です。
Q. 遺品の中に供養してほしい物があるけど、対応してくれる?
A. はい、お焚き上げ・合同供養に対応している業者も多くあります。
位牌・仏壇・人形・写真などは「ゴミ」として捨てづらいものなので、事前に供養の希望を伝えると丁寧に対応してもらえます。
証明書を発行してくれる業者もあり、気持ちの区切りとして喜ばれています。
まとめ|後悔しない依頼のために今できる準備とは?
特殊清掃や遺品整理は“突然やってくる状況”に備えておくべき大切な準備なんです。
「その時になったら考えよう」では遅くて、いざという時に慌てたり、後悔したりする声が本当に多いんですよね。

最後に、これから備えておくべきことを「心構え」「家族との会話」「相談先」「暮らしの安心」という4つの視点で整理します。
“いざという時”に備えておく心構えと知識
まず、誰にでも起こりうるものとして「特殊清掃や遺品整理」を知識として理解しておくことが大切です。
孤独死やセルフネグレクト、突発的な病死や事故など、家族や身近な人に何かあった時、すぐに冷静に動ける準備があるかどうかで対応がまったく変わってきます。
そしてもうひとつ大切なのが、「自分がその当事者になる可能性もある」という意識です。
年齢や立場に関係なく、誰にとっても無関係な話ではありません。

ネットで調べた知識だけでは現場で通用しないことも多いので、専門業者に一度問い合わせてみる・資料を取り寄せてみるだけでも、気持ちの余裕につながると思いますよ。
家族で話し合っておきたい「整理と清掃のタイミング」
「まだ元気だから大丈夫」って思ってるうちは、なかなかこういう話ってしづらいですよね。
でも、“話せるうちに話す”ことが、最終的に一番後悔が少なくなるんです。
たとえば、
-
どんな物は残しておきたい?
-
宗教的な供養は必要?
-
体が動かなくなったらどうしてほしい?
-
死後の家の片付けや管理は誰に頼む?
こういった内容を、元気なうちから話しておくだけで、家族が混乱せずに行動できる準備になります。

相続や介護の話と一緒に、「整理や清掃も含めてどうしたいか」を自然に会話に組み込んでおけると理想的ですね。
困ったときにすぐ相談できる窓口やサービスの例
いざ何か起きた時、「誰に連絡したらいいかわからなかった」と困る方も多いです。
そうならないためにも、事前に相談できる窓口や信頼できる業者をリストアップしておくのがおすすめです。
たとえば、
-
自治体(市役所や保健所):高齢者支援や孤独死後の対応に詳しい部署があります
-
遺品整理士認定協会:認定業者の紹介や相談窓口があります
-
司法書士・行政書士:相続・遺言関連での連携が可能です
-
地元の葬儀社:清掃業者と提携している場合もあります
また、無料相談を受け付けている業者も多いので、問い合わせしておくだけでも安心材料になります。

LINEやメールで気軽に相談できる業者も増えてきているので、使いやすさもチェックしてみて下さいね。
あなたや家族が安心して暮らせる環境を作るために
最後にお伝えしたいのは、特殊清掃や遺品整理って、「誰かが亡くなった時の話」ではなく、「今、自分や家族が安心して暮らすための準備」でもあるということです。
部屋を整えておく、物を減らしておく、困ったときに頼れる人を見つけておく――こうしたことが、結果的に「生きやすさ」に直結してきます。
私たち業者は、作業だけでなく、“その後の暮らし”までを見据えたサポートができるよう心がけています。
だからこそ、必要以上に不安にならず、わからないことは遠慮せず相談して下さい。
あなた自身や大切な人の暮らしが、少しでも安心できるように。

この記事が、その準備のきっかけになれば嬉しいです✨